★東京・大塚★〜管理・売買・賃貸・コンサルティングなど、不動産に関することは何でもお任せください!〜
2014年07月31日
<No 221>
■土用の丑の日

一昨日は、「土用の丑の日」でした。うなぎを食された方も多いかと思います。
土用とは、春夏秋冬各季節の最後の18〜19日を指すそうです。
丑とは、「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥」の十二支の丑です。土用の丑の日が、1日だけの年もあれば、2日ある年もあります。夏はバテやすい時期であることから、「精の付くもの」としてウナギを食べていたそうです。
習慣化したのは、江戸時代後期、万能学者として有名な平賀源内が、夏場にウナギが売れないので何とかしたいと近所のウナギ屋に相談され、「本日、土用丑の日」と書いた張り紙を張り出したところ、大繁盛したことがきっかけだと言われています。丑とウナギ、「う」から始まることもきっかけにある(?)とのことです。
2014年07月22日
<No 222>
■都心に温泉


オフィスビルが立ち並ぶ大手町。昔から日本のビジネスの中心街として、スーツ姿のビジネスマンが行き交うイメージがあります。が、そんな大手町に先ごろ、温泉が湧いたという衝撃のニュースが!
深さ1500メートル付近まで掘削作業が進められ、湧出が確認されたとのことです。温度は36.5度で含ヨウ素・ナトリウム・塩化物強塩温泉を含んでおり、療養泉、治療用にも使われるそうです。そして、温泉が出るからには当然旅館も建築予定で、そこにはフィットネスジムなどが入るとのこと。
名称は「大手町温泉」。
仕事帰りに一風呂はいかが?などのキャッチコピーが早くも出現しています(笑)。旅館となる「星のや東京」は2016年4月にオープン予定。楽しみなスポットになりそうですね!
※写真は、三菱地所 様より
http://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec140715_otemachi-onsen.pdf#search='%E5%A4%A7%E6%89%8B%E7%94%BA+%E6%B8%A9%E6%B3%89'
2014年07月17日
<No 223>
■住まいと通勤

最近、不動産情報サービスのアットホーム(株)が調査した、「通勤の実態調査2014」の結果を公表されました。対象は1都3県在住で都内に勤務する子持ちのサラリーマン583人、とのこと。
その結果、自宅から会社まで片道の平均通勤時間は58分と出ました。住居タイプ別では一戸建てが60分、マンションは56分ほどかかるとのこと。自宅から最寄駅までの平均徒歩分数は一戸建てが14分、マンション10分と差が付きました。
また、通勤時間の「理想」と「限界」について聞くと、「理想」が35分、「限界」86分という結果に。また、通勤時間を有意義だと感じている人は27.1%。苦痛だと感じている人は35.7%。さらに、住宅購入の際に通勤時間よりも優先したことについて聞いたところ、一戸建て購入者の73.0%が「一戸建てであること」と回答し、マンション購入者については、「広さ」が38.9%となり最多となりました。
時間はみんな同じ分だけ流れているので、有意義に使いたい。改めて認識させられました。
2014年07月07日
<No 224>
■動物と暮らし

人にとって最も親しみのある動物に、犬は必ず挙げられます。古くから人と犬の関係は長く、救助犬や盲導犬など様々な人の生活を手助けしてくれる良きパートナーと言ってもいいかもしれません。
そんな犬との生活をもっと深めていこうとしている、ユニークな団体が先ごろ発足しました。その名も「犬と住まいる協会」。とある統計によると、首都圏では1990年頃はペット飼育が認められているマンションは7%だったのに対し、2010年では80%まで増加したそうです。この間、ペット市場は兆単位の経済効果を生むほどになったと言われています。ところが、そんな背景がありながら、ペットと住むための住宅市場はなかなか伸びなかったようです。犬と暮らすためのアイデアや工夫が住宅に取り入れられなかったり、そのような面でのエキスパートが不在だったためです。
同協会は、人と犬が快適に過ごせるための建築やインテリアなどの専門家を育成することを目的としている、とのこと。将来的に具体的にどんなことをしていくのか、興味深いチャレンジです。
※参照 一般社団法人「犬と住まいる協会」
http://www.inusuma.org/
2014年07月01日
<No 225>
■「重要事項説明書」のIT化検討
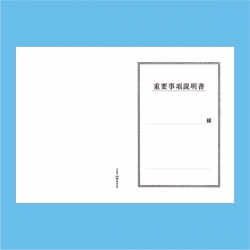
現在、国土交通省では、「ITを活用した重要事項説明書等のあり方に係る検討会」が開かれています。アメリカでは、不動産取引の際に半数以上が電子サインを利用している、とのデータがあるそうです。
重要事項説明書は、売買・賃借・委託契約に関して契約に関する重要事項を消費者に対し説明することです。それをIT化して、重説の録画保存をしたり、消費者・事業者双方の時間やコストを省き取引自体の効率化が図られたり等が可能とのことです。とは言え、賃貸と売買では取引が様々異なる事から、IT活用の課題もあるとのこと。
遠方の方を相手にすることが容易、手間がかからないなどかなりメリットもありますが、直に対面して説明をする・受けるという習慣も大切なことだなぁと改めて考えさせられる問題です。日頃から重説のことを考えながら、今後の動向に注目していきたいと思います。



